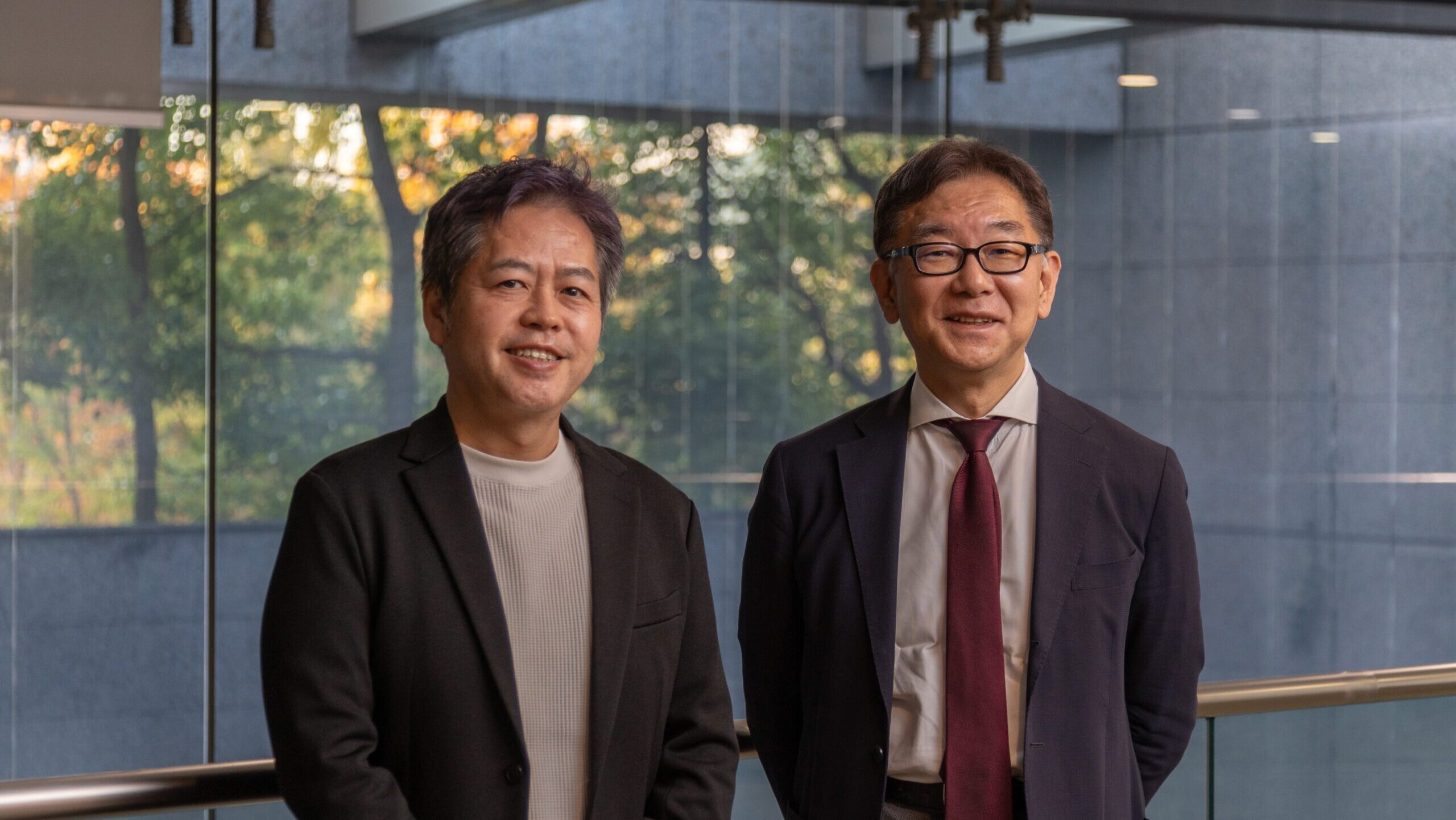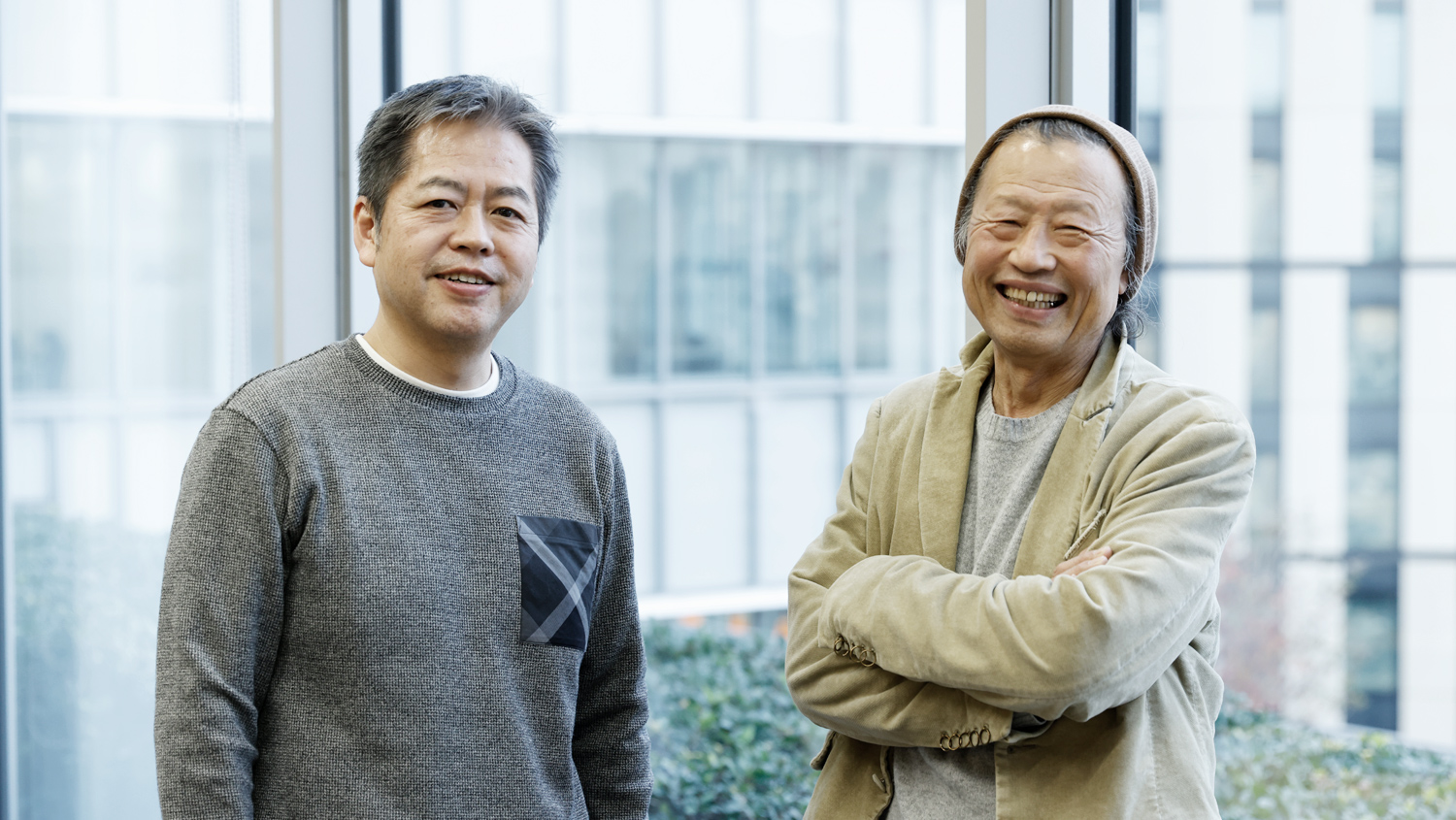
2023.01.12
今こそ小売主導で新たなスキームを創る時(前編)
少子高齢化・人口減少、不況、価格競争が続く日本。食を取り巻く環境は、生産者と小売業者、どちらも恵まれているとは言いがたい現状です。高品質なものをつくり出す、高精度の技術を持ちながら、事業の先行きが見通しにくい状況にあるのではないでしょうか。
アットテーブルは食のマーケティング支援会社として、このような時代の中で生産者と小売業者のあるべき関係について、先駆的な取り組みをしている方や識者を招いて学び、課題やそれを解決する方向性についてともに考えていきます。

福島 徹(ふくしま・とおる)
株式会社 福島屋 代表取締役会長
1951年東京都生まれ。家業のよろず屋を継ぎ、酒屋、コンビニを経て、34歳のときに現在のスーパーマーケットの業態へ転換。安売りをしない、チラシを配らないという独自のスタイルを貫き、自ら産地へ赴き、生産者から直接米や野菜を仕入れ、つくり手とのコラボレーションによる福島屋オリジナル商品を多く開発。“食のセレクトマーケット”として多くのファンに愛される店づくりを行っている。

上田 健司(うえだ・けんじ)
株式会社 アットテーブル 代表取締役社長
1993年DNP入社、商業印刷の営業に従事。新規得意先開拓を得意とし、食品小売および食品メーカー、CVSなど独自の戦略で数多く開拓。2004年にDNPの社内起業制度にて株式会社アットテーブルを一人で創業。独自の食卓分析やトレンド情報分析とクライアントPOS分析等を比較融合した独自のMD計画作成支援を発案。日本全国の大手食品小売や食品メーカー、宅配関係.および各種商業施設の戦略コンサルティングやMD支援を手掛ける。2014年よりMDを核にしたブランディング支援として、戦略立案から計画立案および一貫したプロモーション提案を行う「ブランディングMD」を推進。2015年度より食に関わる社会課題の解決に取り組み、勉強会やセミナー、それらのFSの場として市谷に@MARCHEを出店、現在に至る。
日本スーパーマーケット協会 次世代販促セミナー、同協会アニュアルセミナー、ダイヤモンドセミナー、コーネルJAPAN、リテールテックJAPANなど講演多数。
お客様に「わあ、これいいね」「ここいいね」と感じてもらえる品ぞろえと店つぐり
第1回は、羽村市を拠点とし、スーパーマーケットや飲食店などを都内に展開する福島屋の福島徹会長をお招きしました。
福島会長は、自ら全国の産地を訪ね、その眼鏡にかなった食材を仕入れ・加工して販売してきました。そして、その食材・商品がなぜおいしいのか、どうしたらおいしく食べられるかを消費者に伝え続けています。いわば生産者と消費者をつなぐ食の世界の翻訳者であり、アットテーブルが考える理想の小売業を展開されている方です。
その福島会長に、日本の食の現状と課題、そして課題解決に向けて小売業が果たせる役割は何かをうかがいます。
上田 日本の食を取り巻く環境が、非常に混沌としていると私は感じているのですが、今の食が抱える課題を会長はどう見ていますか。
福島 さまざまな要因がからみ合って複雑な状態です。課題もたくさんあって、ひとつを解決すればすべて良い方向へ行くとも思えない。単に良いものを売ればいい、あるいは品ぞろえを豊富にして選んでもらうという従来の小売りスタイルでは、なかなかお客様に応えていただけなくなってきたということを、強く感じています。
上田 原材料費に加え、物流コストも光熱費も高騰し、メーカーの値上げも相次いでいます。にもかかわらず、小売りでは相変わらず価格競争が続いています。最近では、198円弁当などを出すスーパーも出てきました。こういう状況をどう思いますか。
福島 198円で弁当を成り立たせるのは、相当な企業努力をされてのことだと思います。人は三度三度、食事をとりますが、毎回調理に手間暇とお金をかけられるわけではないし、家計が苦しい家庭も増えてきているので、そこはお客様が上手に使い分ければいいと思います。ただ、お客様がうまく使い分けができるような小売り業態の多様性は大切ですね。
上田 私も気にかけているのはそこです。小売りも大手になると1店舗の商品は1万数千点もあり、年商は数千億円にもなります。けれども利益率は1パーセントに近いひと桁だったりする。今のような状況が続くとすれば、そうした業態を持続できなくなるのではないかと思うのです。
福島 確かに維持していくのは難しくなるでしょうね。
上田 ちなみに福島屋の1店舗あたりの商品数はどのくらいですか。
福島 5000~6000点といったところです。
上田 かなり絞り込まれているのですね。なぜそのようなかたちにしたのかを、少しお聞かせください。
福島 そもそも吹けば飛ぶような小さな会社で、とても大手に太刀打ちできませんから、大手と同じようなやり方はやめようと考えたのが出発点です。それと、自分がいいと思うもの、お客様に「わあ、これいいね」と感じてもらえる品物だけをそろえて「ここいいな」と言ってもらえる店づくりをしようと考えてきました。

生産者と消費者をつなぐのが小売業 売ることより「伝えること」を重視
上田 「わあ、これいいね」というのは感覚的、情緒的な評価ですが、どのようにしてお客様からそのような反応を引き出していくのですか。
福島 例えば店の仕入れアイテムに青森の焼き干しがあります。現地のおばちゃんたちが、昔ながらの手法でつくっているのですが、地方が衰退するなかでもそういう伝統的なものは残っています。手間をかけたものなので、もちろん品物もいいのですが、それをつくっているおばちゃんたちがまたいいんですよ。そうした伝統や手づくりの情景なども含めてスタッフと共有し、お客様に伝えていくというようなことです。
上田 なるほど、確かに福島屋の売り場には、書店で本を探しているときのような対話的な楽しさがあります。
福島 対話的であることは、常に意識してきました。
上田 会長は商品を売るというより、それが何であるか、どうつくられているかを「伝える」ことに力を入れてこられた。それは人間がいかに食を大切にしてきたかを、商品を通して語ることでもあると思います。もともと小売業、街の個人商店などは「商品を通して語る」ことを大切にしていましたから、ある意味で福島屋のスタイルは原点回帰ともいえるのかもしれませんね。

福島 今は効率が求められるので、商品づくりも売り方も、システマティックになっています。それはやむを得ないことだとは思います。けれど、食は五感に刺激を受けて、五感で感じて楽しむものですから、その世界がどんどんシステマティックになっていくと、食品が単なるビジネスツールのようになってしまいます。それをさびしく思う方もいるのではないでしょうか。消費者全体からすればそれは少数派で、数も減ってきているのかもしれませんが、効率第一ではない商品、食品を強烈に求めている方はけっこういると思います。その潜在しているニーズを掘り起こすとなると、僕は売り場や商品は僕らの感性を表現するツールだと思っていますから、それがきちんと表現されているかどうかが非常に重要になってきます。
上田 売り手の感性をどう表現するか……、それはとても興味深い。
福島 先日、芸大(東京藝術大学)で先生と対談する機会がありました。アートの視点を支えに、何かコラボレーションできればいいですねという話をしたのですが、アートも五感で楽しむものですから、食と通じるものがあります。今はコロナ過や戦争などもあって、誰もが何かしらの社会不安を感じていています。そういう状況下での小売業は、売り場づくりや品揃え、あるいは商品開発や商品のトレンドを読むうえでも、感覚、感性といったものがますます大切になってくると思うのです。
上田 食を取り巻く現況を考えるとき、感覚、感性というのはひとつ、課題解決へ向けた重要なキーワードになりそうですね。

今こそ小売主導で新たなスキームを創る時(後編)